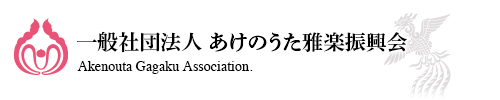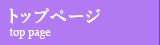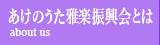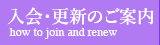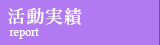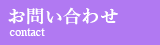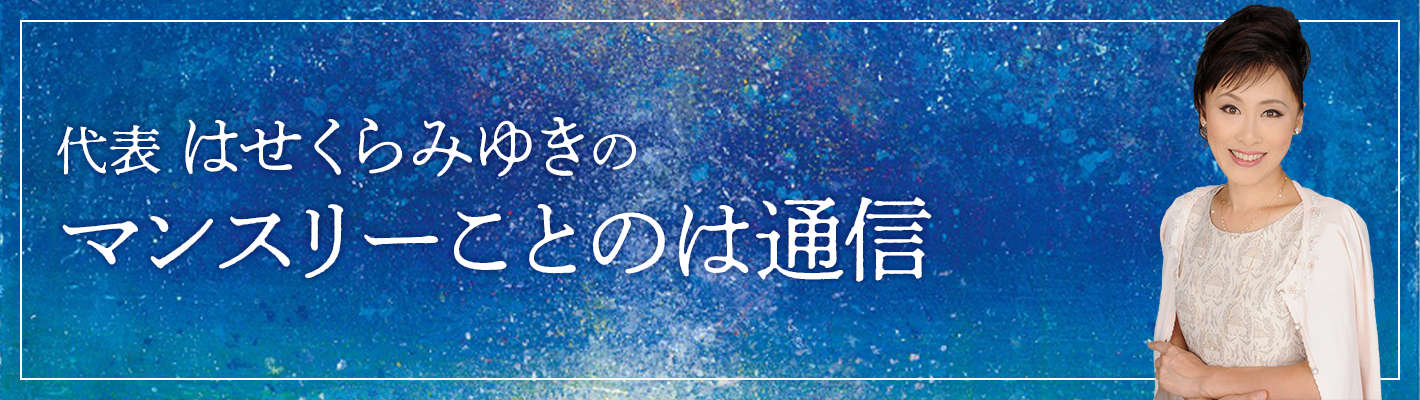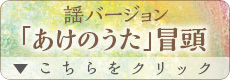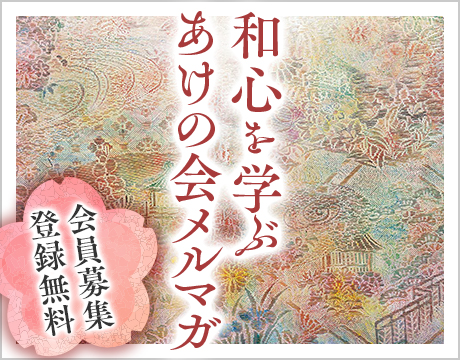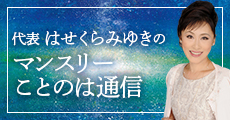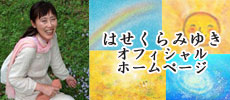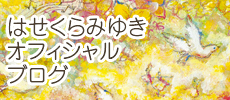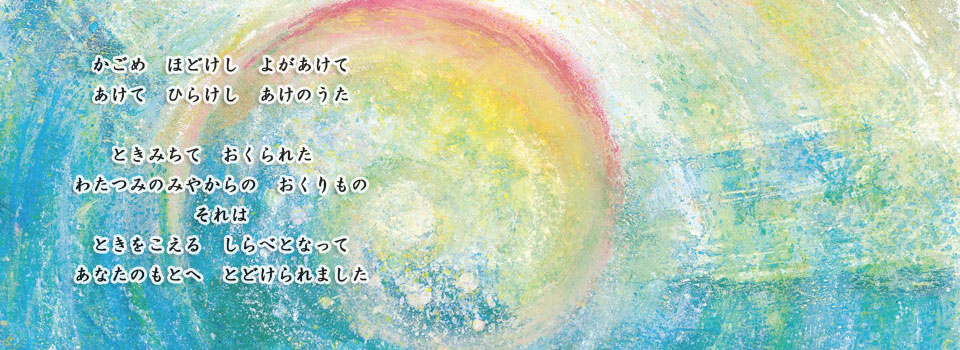
あけの会 マンスリーことのは通信2025年8月
皆様、こんにちは。
お元気ですか?
毎日暑い日が続いておりますが、
いかがお過ごしのことでしょうか?
暑い日が続くとどうしても冷たいものがほしくなりますが、
取りすぎてしまうと調子がくるってしまうことがあります。
出来るだけ身体自体は冷やさないように、
冷たいものは控えめにして、ご自愛くださいね。
ちなみに、私はかつて氷を食べていて、
そのあと、貧血になったことがあります。
病院にいくと、「氷」は鉄分を壊すんだよ、といわれ、
びっくりして、以来、あまりとらないようになりました。
もちろん暑いと、ガリガリしたくなりますが、
どうぞ控えめにされてくださいね(←余計なお世話ですみません!)
さて、今日は基本に立ち返って、
神楽とは何かについて触れていきたいと思います。
神楽(かぐら)とは、神様にささげる舞と楽の歌舞のことです。
その起源は、遠く古事記の神話にさかのぼります。
それは、皆さま、よくご存じの
天照大神が天岩戸にお隠れになったときのお話がもとになっています。
世界が暗闇に照らされて困り果てていた時、
神々は神譲り(話し合い)を行うことによって、
天鈿女命(あめのうずめのみこと)が岩戸の前で舞を舞い、
神々が笑い、喜び、音を鳴らし、ついには天照大神が岩戸を開いた——
この神話が、神楽の源であるといわれているのですね。
このように、神楽とは、音と舞によって世界をよみがえらせる行為であり、
人と神様とが一緒になって踊り、笑い、響き合うことで、
いのちの光をもう一度呼び戻す、再生の儀式でもあるのです。
尚、神楽は全国各地にあり、その土地ごとの自然、暮らし、神話が溶けあって、
さまざまなかたちで継承されています。
大きく分けて神楽の種類は三種類に分別されます。
1 御神楽(みかぐら):宮中などで神に奉納される正式な儀式舞。静かで荘厳。
2 里神楽(さとかぐら):地方に根づいた民間の神楽。
3 出雲神楽・岩戸神楽・伊勢神楽など:それぞれのかたちで舞い、神話や伝承がある。
ピンと張りつめた空気の中で、心を天に預け神様の御前で神楽を奉納する、ということ。
それはまさしく「神の神聖」に触れている瞬間なのかもしれません。
今年は伊勢神宮でのご奉納が待っています。
それぞれの御魂を磨きながら、清々しき御神気と共に、神楽ご奉納を味わい愉しみたいと思います。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
さて、最後に今月の雅楽をお届けします。
8月の雅楽は、『捨翠楽』(じゅっすいらく)という楽曲です。
もとは水調という調子であったらしいのですが、
現在は夏の季語である「黄鐘調」の曲とされています。
龍笛の音が高音で、耳の奥を刺激し、高次元へといざなうような響きだなぁと、
いつも感動してしまいます。
それほど長尺ではありませんが、心地よい響きですので、ぜひお楽しみくださいね。
それではどうぞお元気で。
善き八月をお過ごしくださいませ。