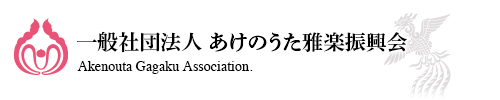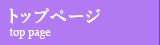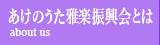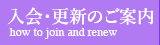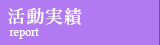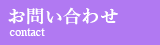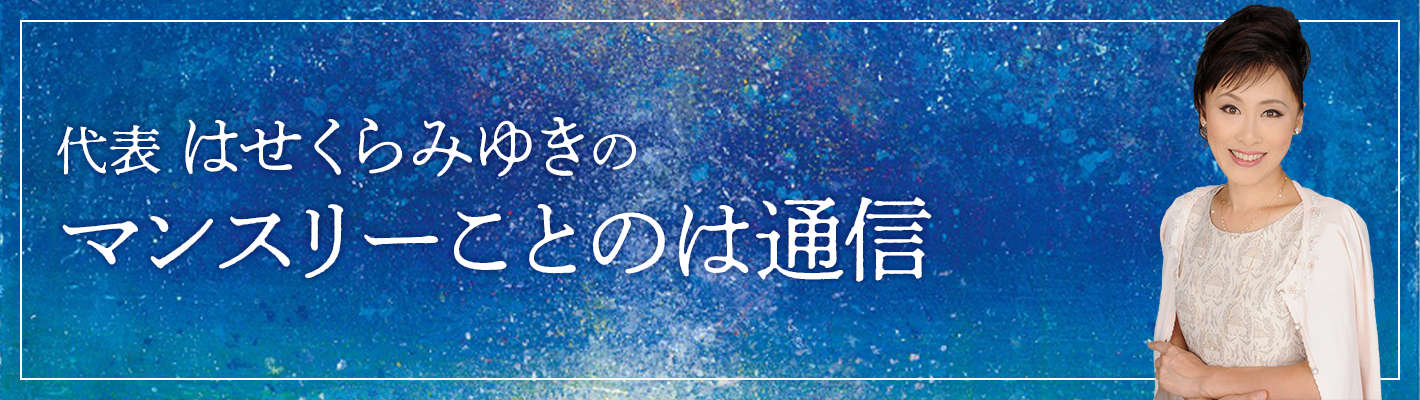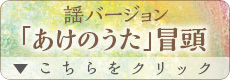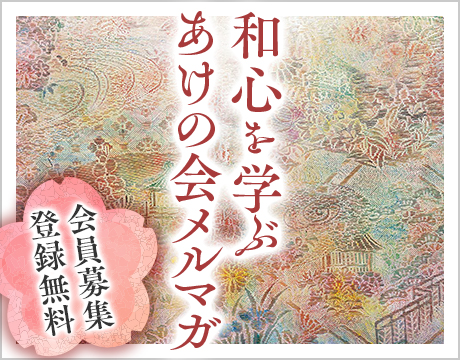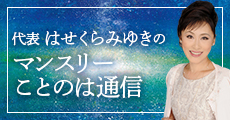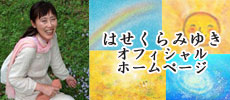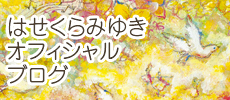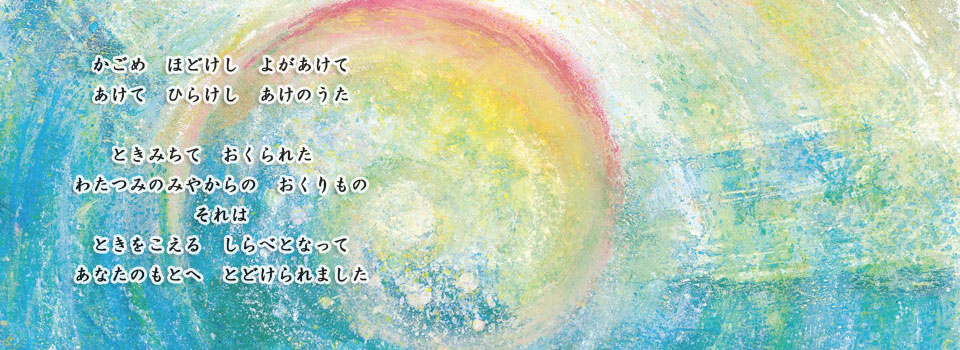
あけの会 マンスリーことのは通信2025年9月
皆様、こんにちは。お元気ですか?
今、私は諏訪に行く特急の中で、この通信を書いています。
私のような仕事は、重なる時は思いっきり重なるのですが、
無い時は無いという、粗密が激しい(笑)日常を過ごしています。
8月下旬より、なぜか関東をはさみながら
東北と長野を往ったり来たりしています。
そこでは主に「縄文」に触れているのですが、
知れば知るほど「縄目の文様」を刻んだ人々の、
精神性の高さと穏やかで、SDGsな暮らしに圧倒されます。
先日も北東北の縄文遺跡を巡っていたのですが、
漆の文化が9000年前からあった(世界最古!)ことを思うと、
言葉にできぬ圧巻な想いに包まれます。
合掌土偶で有名な是川遺跡(八戸)にある縄文館では、
そんな漆で出来た弓矢や櫛、注口器(やかんのような土器)などが、
数千年の時を経て、まだ使えるんじゃないかという
色味と形を残しながら、鎮座していました。
ちなみに弓は、ご想像の通り狩猟の道具でありますが、
それを初めて持たされた男の子(たぶん)の
誇らしげな姿が目に浮かぶようでしたし、
美しく装飾された櫛が、愛する人から贈られた時の、
女子の心はいかばかりだったかと思うと、
時を超えても変わらぬ人の機微を思い、
胸がいっぱいになりました。
それにしても「漆」の技術をいかにして、古代人は知ったのでしょうか?
漆はかぶれますし、純度の高い漆を精製するには、
いくつもの複雑な工程が必要で、
そうそう簡単に出来るものではないのです。
でも、出来ている。それが「事実(ファクト)」です。
ここからは想像になりますが(というか内なる叡智との対話です)、
彼らは「植物と対話していた」からであるとのことでした。
いにしえの御代は、植物(ここでは漆の木)や岩、木と、
心の奥で対話しながら、微細な気配や兆しといったものを見逃さず、
長きにわたって粛々と、そして生の喜びをあるがままに発露しながら、
生きていたのであろうと推測されます。
こうした自然界のものたちとの対話が残されている記述が、
大祓の中に描かれています。
それは「事問ひし磐根樹根立草の片葉をも語止めて…」
という部分です。意味を簡単に説明すると、
岩や根っこや木々たちや草木に至るまで事の真意を問うと、
彼らはお喋りをやめて…という意味合いになります。
えっ、古代の人たちは草木とおしゃべりしていたの?
ということになりますね。こんなふうに祝詞を読み解いていくのも
面白いですが、縄文人たちの漆のお話に戻しますと、
そんな漆の技術が、やがて遥か海を渡り、南米大陸にまで、
伝えられたという説もあるのです。
それは現地の人たちの伝承からなのですが、
遠く海を渡ってきた人たちから、「ゴム」の木から、
ゴムを取る技術を教わったと。
その技術が漆を作る技術とよく似ているのですね。
そして、彼らが大切にしている聖なる湖―チチカカ湖は、
「お父さん・お母さん」という意味なのだということです。
…とロマンが広がるお話でありますが、
今、古代人の叡智が呼び覚まされようとしています。
そしてその本質的な部分が、
「共感」と「共創」です。
様々なものと心を通い合わせる素朴で真摯なる心。
共に力を合わせて何かを創り出す共創の心。
あけの会の活動も、こうした「共感」と「共創」の実践の場、
ではないだろうかと感じています。
巷を見渡すと、本当にこのままで大丈夫か?
日本は、世界はどうなってしまうのだろう?といった、
混迷混乱の様相を示しているように見えますが、
縄文を含むかつてのいにしえ人が、
どんなことがあっても、諦めることなく、逞しく
未来への歩を進めていったように、
その遠き子孫である私たちも、
子々孫々へと続く素晴らしい時代を創る担い手として、
今まさに生きる本番を迎えている、
ということなのかもしれません。
明るく強く逞しく、共に手を携えながら
進んでいきたいと思います。
さて、今月の雅楽です。
今月は「催馬楽」をお届けしたいと思います。
催馬楽(さいばら)とは、平安時代の宮廷で愛された、
日本独自の歌謡です。
日本の各地の民謡を雅楽の旋律と楽器で編曲したもので、
歌詞は大和の言葉がおりなすの素朴な民謡が中心です。
一音を長く発音するため、少し眠たくなってしまうかも⁉ですが、
かつてはこうした楽曲を聴いて、楽しんでいたのでしょうね。
ただ、「周波数」という観点からみると、
一音を長く発語することで、その音の響き(固有振動)が、
しっかりと届くので、心身にも良い影響があったんじゃないかな、
と推測してしまう現代人のはせくらです。
ちなみに歌の内容は、庶民の恋愛や日常生活の感情を、
朗々と歌い上げているんですね。
というわけで催馬楽 「更衣」です。
まったりされましたか⁉
それでは今月はこの辺で。
皆様どうぞお元気でお過ごし下さいませ。