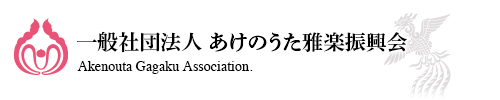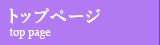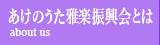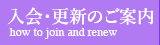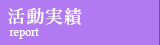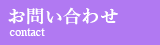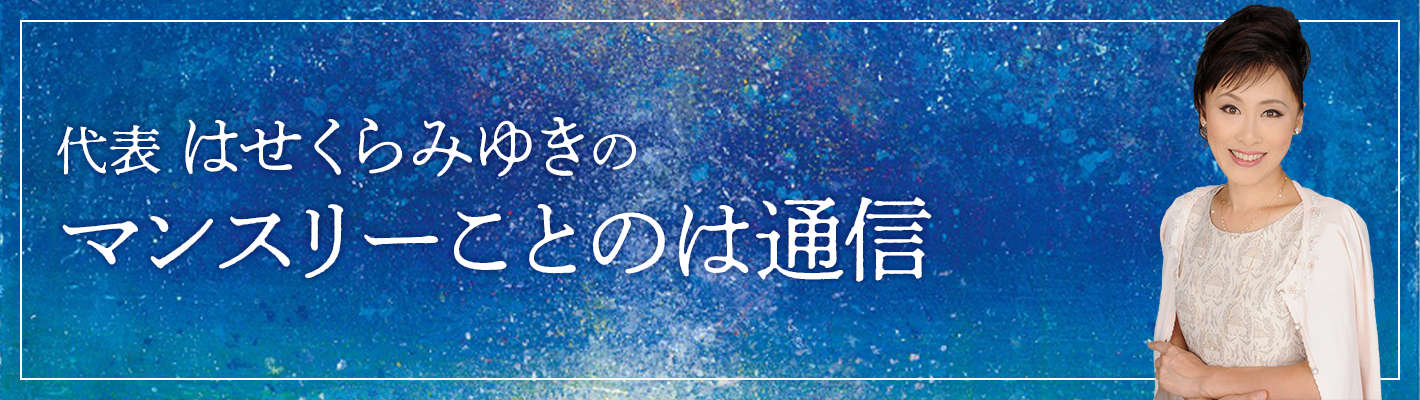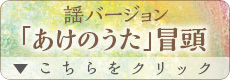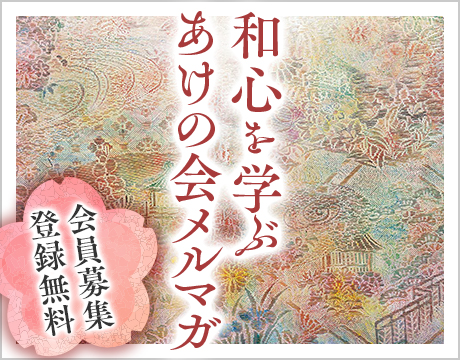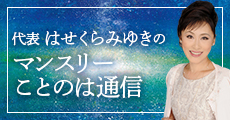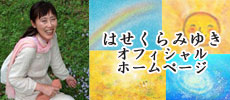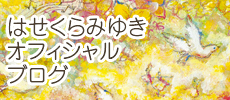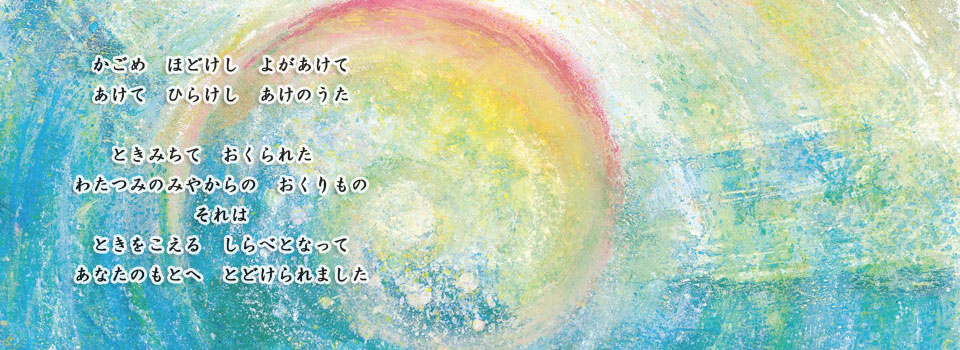
あけの会 マンスリーことのは通信2025年7月
皆様、お元気ですか?
夏越の祓も終わり、夏真っ盛りと季節となりました。
これから暑くなりますが、皆様どうぞ水分はしっかりととって、
暑さに負けず、元気にお過ごしくださいね。
あけの会では、今月、夏季研修会があり、午前中から、
神楽奉納に向けてのお稽古に励みます。
今年の秋に奉納予定の舞台に向けての全体稽古として、
それぞれの持ち場で頑張っています。
雅楽の音色に包まれながら(日常とは全く違う雰囲気になります)、
過ごすときが、ゆったりとしながらも緊張感があり、
得難い体験だなぁと、毎回、静かな喜びに包まれます。
さて、ここからは「暦」のお話をしたいと思います。
皆さま、よくご存じであるとおもいますが、年代の表記には、
西暦と和暦があります。
実際の表記としては、西暦の方が使いやすく簡単なのに~と思うことがありますが、
和暦である元号を使った表記は、「大化の改新」(645)以来、
1300年以上もの歴史を持つ、日本独自の貴重な暦法であります。
現在までに248もの元号がつかわれているのですが、
「あれ? 歴代天皇の人数より多くない?」と不思議に思われた方も、
いらっしゃるかもしれません。といいますのは、
おひとりの天皇様につき一つの元号を用いるという、
一世一元のありかたとなったのは、明治以降なのですね。
それまでは、何か大きな出来事があったとき(良いことも悪いことも)には改元する、
ということをしておりましたので、248となっているというわけです。
元号はわが国独自の暦法となっていて、
その名前の奥には祈りや願い、そしてどうありたいかという、
希望の思いが、「予祝」となってはいっていると感じます。
現在であれば、「令和」ですので、令という神意に沿った生きかたをすることで、
和らぎの国、そして和らぎの世界をもたらしていく、という
祈りと意思を感じます。
ですので、堂々と、誇りをもって「元号」を使いたいなと思います。
もちろん、なんでもかんでも元号に…といった野暮は申しません(笑)。
臨機応変、融通無碍というのも我が国の得意とするところでしょう。
ちなみに西暦の表記ですが、私たちは一般的に、
キリストが生まれた年として記憶しています。
…が、詳しく調べてみると、どうやらキリストが生まれたのは、
AD1年ではなく、BC4年ではないか、というのが
その後の研究で分かってきています。
また、BCは、ビフォーキリストで、この言い方は18世紀から、
そしてADというのはAnno Dominiというラテン語で、
「主の年」という意味で、6世紀のローマの神学者によって、
考案されました。なぜラテン語だったのかというと、当時の公用語が、
ラテン語だったからです。
というわけで、時を刻む「暦」の表記のお話でした。
まさしく今、歴史に残るであろう、時が刻まれていることを感じます。
そんな大切な一幕を、我として今此処に生を受けている奇跡を思います。
大切にそれぞれのときを刻んでいきましょうね。
では最後に今月の雅楽です。
では今月の雅楽です。
今月は「長慶子」です。安倍晴明の友でもあった、
源博雅(みやもとのひろまさ)が作曲したといわれる
楽曲です。まさに雅な旋律ですよね。(音楽のみですのでBGMとしてどうぞ)
こちらの楽曲は、雅楽演奏会の退出曲としてよく使われます。
この曲を聴くと、また演奏会があったら行きたい~!
という気持ちになってしまうんですよね。(途中、睡魔が襲うこともあるのに、
わがままなものですね…笑)
それでは今月も佳き月でありますように。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。